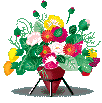ゲノム情報を病気の診断や治療に役立てようと世界中で研究が進んでいる。病気に関係する遺伝子を突き止めて、その働きを明らかにする。多くの遺伝子と生活環境がからみあった病気が発病する仕組みをあきらかにする・・・・。 ただ、ゲノムを読み取っても、すぐに病気の治療に結びつくわけではない。明らかにされたのは文字の並び(塩基配列)にすぎない。意味のあるデータにする研究はこれからが本番だ。
ヒトの体をつくる細胞には二十三本の染色体が二セットずつ含まれる。
染色体のどの場所にどんな遺伝子がのっているのかはすべてのヒトに共通している。
だが、遺伝子のなかの文字の並び方までまったく同じというわけではない。顔つきが違うように、個人によってわずかな違いがある。
個人差を示す並び方の種類はいくつかある。[CACACA・・・]というように短い塩基配列の繰り返す回数が、個人によって異なる「マイクロサテライト」もその一つだ。
猪子英俊・東海大教授(分子遺伝学)らは、これを目印に、病気とのかかわりの深い遺伝子をみつけようと研究している。
病気の関連遺伝子と一緒に伝わる特定のマイクロサテライトの型を探し、その付近の遺伝子を詳しく調べるのだ。ゲノムの塩基配列がわかっていれば簡単。これを今夏までに約3万個見つける予定だ。
この方法で6番染色体を詳しく調べ、皮膚に発疹ができる尋常性乾癬や慢性の炎症が起こるベーチェット病に関連する遺伝子をそれぞれ突き止めた。リウマチにかかわる遺伝子もあと少しで見つかりそうだという。
(後略)
(朝日新聞二月十四日号より)
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
朝日新聞に久しぶりに尋常性乾癬の文字が目につきました。人体の設計図といわれるヒトゲノムの解読をめざす日米欧中の国際ヒトゲノム計画チームと、米セレラ・ジェノミクス社が競い合って概要を読み取り、それぞれ英米の科学誌に論文が掲載されるそうです。
遺伝的素因が疑われながら、原因が不明とされてきた乾癬に二十一世紀初頭にして遺伝子レベルでの解析が進捗してきました。
われわれ、乾癬患者としてもその研究成果に大いなる期待と関心を持ち、一日も早く治療レベルでの応用研究に拍車がかからんことを祈るばかりです。
そこで、ヒトゲノムとは何ぞや?遺伝子とは遺伝情報とは?との疑問にお答えして、遺伝に関する基本の解説を次にまとめました。
◇ヒトゲノムとは何ですか?
「ヒトゲノム(Human
Genome)」のうちヒトは人間をあらわしています。「ゲノム」はある生物種がもっている遺伝情報の全体をさす言葉で、その生物種の全部の遺伝子をふくんでいます。
つまり、ヒトゲノムとは人間の体をつくる設計図と呼んでも差し支えないでしょう。
◇なぜ人間とはいわずにヒトと呼称するのですか?
生物学では全ての生物種の名前を日本語ではカタカナで表記することになっています。
◇遺伝子とはなんですか?
親のもつ種々の性質や形質が親から子へと伝わる現象を【遺伝】といい、遺伝をつかさどる因子を遺伝子とよびます。
◇ 遺伝学と遺伝物質について
生物が遺伝することは経験的に昔からわかっていたことですが、オーストリアの神父メンデルがエンドウ豆の交雑実験による「メンデル遺伝の法則」を確立したのは今から約130年前の1866年のことでした。しかしいったい何が遺伝情報を伝えるのかはずっと不明のままでありました。
ところが、1928年、グリフィス博士という研究者が遺伝が化学物質で決まることを証明しましたが、この時点では遺伝物質が何であるのかまではわからないままでした。この遺伝物質についてはいろいろな科学者が論争をし、DNAかタンパク質であろうと結論が絞られました。
DNAは糖とリン酸、4種類の塩基でできた単純な物質で、タンパク質は非常にたくさんの種類がある複雑な分子であるため、当初は遺伝子本体の物質はタンパク質であろうと間違った推測がされていたのです。
◇遺伝物質がDNAであることが解明されたのはいつですか?
アメリカの細菌学者アベリー(エイブリー)が共同研究者と共に10年がかりで遺伝物質がDNAであることを突き止め、1944年実験医学雑誌「ジャーナル・オブ・エクスペリメンタル・メデイシン」誌に発表しました。
◇DNAとはそもそも何ですか?
すべての生物はその生物の固有の遺伝情報をもっていて、その情報にもとづいてからだがつくられ、維持されています。遺伝子情報の基本的単位は細胞の中にある遺伝子で、からだを構成するすべての細胞に一個ずつ存在し、その実態がDNAなのです。しかしそのDNAすべての部分が遺伝にかかわっているわけではありません。その97%は何の意味もない「がらくた配列(ジャンク)」と考えられています。現在一万個程度遺伝子が見つかっていますが、さらに将来発見されると予測される遺伝子を含めると、最近の研究による予測数ではおよそ三万個〜十四万個程度あると考えられています。
しかし、その「がらくた配列」を含め全てのDNAの塩基配列をもれなく明らかにしようとするのが、国際ヒトゲノム計画なのです。
DNAは【デオキシリボ核酸】の略です。英語では【Deoxyribo
Nucleic
Acid】。デオシキリボはデオキシリボースと呼ばれる五つの炭素を使った糖(5炭糖)が重要な構成物質で、これが名称の由来です。
DNAは細胞の核の中に存在し、デオキシリボース(糖)と、リン酸(P)が二重らせん構造をつくっている分子です。DNAは遺伝情報をあちらこちらに散りばめた核と相対的に比較すると、とてつもなく長いロープ?なのです。
◇新聞記事中のマイクロサテライトについて説明して下さい。
「がらくた配列」の中には前述の短い塩基配列の繰り返し[CACACA・・・]が何十回と繰り返される部分があり、これをマイクロサテライトと呼びますが、ゲノム地図を作成するときにはこの「マーカー」(目印)」が極めて、役に立つ存在となります。
◇二重螺旋(らせん)構造とは?
DNAの構造を具体的に表現するもっとも有名なキーワードで、アメリカのジェームス・ワトソンと英国のフランシス・クリックという2人の生物学者が細胞の中のDNA(デオキシリボ核酸)の分子構造を解明した功績で、1962度のノーベル医学生理学賞を受賞しました。
二重らせんはアメーバからヒトに至るまで、全ての生物のDNAに共通した構造で、らせんは、ヌクレオチド(nucleotide)糖(デオキシリボース)とリン酸が結合したもので、反対向きの2本のらせんのそれぞれから出た塩基が互いに結びついて二重らせんを形成しています。塩基はAはTと、GはCと必ず結合し、それらを結び付けているのは水素結合という弱い結合です。二重らせん構造の特徴である塩基間の特異的水素結合による相補的塩基対の形成と、2本のDNA鎖の双極性(互いに逆位平行していること)は、二重らせん構造そのものが複製可能な物質であることを示しています。
◇ 相補的塩基対の形成とは?
2本のらせんの一方の鎖の塩基の配列を決めると、他方の塩基の配列が自動的に決まることです。一方の鎖が他方の鎖の鋳型(いがた)になることが、遺伝子の複製を可能にするまことに巧妙な仕掛けなのです。
◇二重らせん構造は具体的にどのような形ですか?
DNAは縄ばしごを縦方向にねじったような形をしています。縄ばしごが真っ直ぐでなく、くりくりと捻られている形をイメージして下さい。
遺伝子の解説書を見ていただければさまざまな絵図が書かれていますが、代表的な分かりやすく美しい図を次ページに掲載しました。ご参照ください。(注:図は会報8号をご覧下さい)
◇核酸とは何ですか?
前述の糖、後述の塩基、リン酸からなる高分子物質で、核に多く存在する酸性の物質と言う意味で核酸と名づけられました。核酸にはDNA【デオキシリボ核酸】とRNA【リボ核酸】があり、どちらも遺伝情報をになう物質として細胞内でとても重要な働きをしています。核酸はあらゆる生物の中の細胞の中にあり、遺伝子の本体として細胞の分裂、成長をコントロールしています。
◇RNAとは何ですか?
RNAは【リボ核酸】の略です。英語では【Ribo
Nucleic
Acid】。リボとはリボースと呼ばれる五つの炭素を使った糖(5炭糖)が構成物質で、これが名称の由来です。DNAと共に遺伝機構の本体をなし、タンパク質の生合成に関与、DNAの遺伝情報の保存や複製に仲介役として活躍し、メッセンジャーRNAやトランスファーRNAと呼ばれるものがあります。
◇DNAとRNAの関係を分かりやすく説明して下さい。
DNAは遺伝情報を満載したマスターテープ。RNAはDNAの情報を複写するためのダビング専用テープのメッセンジャーRNAとタンパク質の材料となるアミノ酸を運んでくるトランスファーRNAがあります。
◇メッセンジャーRNAとかトランスファーRNAとは何ですか?
複雑過ぎてこれ以上説明は困難ですが、メッセンジャーRNAとは伝令RNAとも言い、遺伝情報をDNAより転写して、翻訳する役目をします。トランスファーRNAとは運搬RNAともいい、メッセンジャーRNAの情報に似合うアミノ酸を運んでくる役目をしています。
このmRNAとtRNAとリボソームが関与して生命活動に必要なタンパク質をつくりだしています。
◇DNAは具体的にどのような遺伝情報で書かれているのですか?
DNAとかRNAの遺伝情報をつかさどる文字はたった4種類しかない。「ウッソー」という読者の声が聞こえてきそうですが、事実です。4文字の極めて単純な組合わせが何億、何十億と続いて生物の遺伝情報を決めているのです。
◇その4文字とは何ですか?
DNAは RNAは
€アデニン【A】 €アデニン
グアニン【G】 グアニン
¡シトシン【C】 ¡シトシン
¤チミン 【T】 ¤ウラシル【U】
これらの塩基の配列が遺伝情報を表しているのです。
◇DNAとRNAでチミンとウラシルだけが違うのはなぜですか?
何か意味があるように思いますが、現在の研究では理由がはっきりしません。DNAが採用しているチミンとRNAが採用しているウラシルの差はチミンにメチル基があるだけでアデニンとの水素結合能力についてはさほど差はないと考えられていますが、現時点では理由不明です。
◇塩基とは何ですか?
塩基というのは、窒素原子(N)を含んだあるタイプの有機化合物のことをいいます。アルカリ性。塩基はDNAやRNAの構成成分で、プリン塩基(アデニンとグアニン)ピリミジン塩基(シトシン、ウラシル、チミン)に大別されます。これらの物質は塩基性の性質をもつところから、このような名前がつけられています。DNAやRNAの遺伝情報は、これら数種類の塩基の並び方によって決められています。
◇塩基配列とは何ですか?
DNAを構成する塩基には、アデニン、シトシン、グアニン、チミンの4種類、そしてRNAの塩基には、チミンの代わりにウラシルがありますが、これらの塩基のDNA鎖やRNA鎖の上での並び方を指します。この配列こそが遺伝を決定づける遺伝子そのものといえます。ヒトにはこの配列が30億対あるといわれています。この30億対の配列をコンピュータ【DNAシークエンサー】DNA塩基配列自動読取り装置で読み取っていく作業がヒトゲノム計画なのです。
◇前述の30億対の配列?についてもう少し踏み込んで説明してください。
ヒトの細胞1個の核に含まれる遺伝子の基本情報量は30億の化学の文字で書かれており、これを仮に本にすると何と千ページの本で千冊分に匹敵する膨大な情報が書かれていることになります。
これだけの膨大な情報量をもった遺伝子が、60兆個の細胞のひとつひとつに全く同じ情報として組み込まれているということは、体のどこの細胞の一片をとってきても、そこから人間ひとりを立派に誕生させることができる可能性を秘めているということにもなります。
◇染色体とは何ですか?
顕微鏡の進歩によって細胞の核の中まで鮮明に見ることができ、核の中の染色体が今から百十年も前に発見されていたのは驚きです。ヒトの体細胞の染色体を光学顕微鏡で眺めると、Xないしは【やっとこ】の形をした四十六本の大きさのまちまちの棒状のものが確認できます。
一八八八年ワルダイヤーによって発見され染色体と命名されました。高等生物のDNAはタンパク質とともに細胞分裂の直前に、染色体という束にまとめられます。よく観察すると、そのうちの二本づつは同じ形をしています。同形の対は【相同染色体】と呼ばれそれぞれ父と母から受け継いだものであります。
染色体は対で長さの長いものから短いものの順番とその形により第一染色体から第二十二染色体まで名づけられ、これを常染色体とよんでいます。二十三番目は性染色体として別格扱いです。
【染色体挿入図】(注:図は会報8号をご覧下さい)
◇染色体の名の由来は?
人為的に塩基性(アルカリ性)の色素(ギムザ液)で染めることができることが語源です。光学顕微鏡で観察する時には、観察対象物を各種の化学物質で染色して観察しやすくすることはごく普通のことです。
◇DNAと染色体の関係は?
DNAは二重らせん構造をしていますが、その実際の太さに比べて気の遠くなるほどの長さのDNAは、巧みに折りたたまれ細胞の中の核の部分に顕微鏡で視認出来る染色体として存在しています。一個の細胞に含まれる片方の親から受け継いだDNAの鎖をすべてつなぎ合わせると70センチメートルにもなります。仮にこのDNA鎖を50万倍に拡大すると、その太さは直径1ミリのタコ糸のようなものになりますが、その長さはなんと350kmの長さになってしまいます。
◇遺伝子は結局どこにあるのですか?もう一度説明して下さい。
遺伝子は細胞の核の中の染色体にあって、染色体を構成するDNA分子の特定の領域(およそ3〜5%の部分)であり、その特定の領域のDNA塩基配列が人体の設計図であるといえます。
それぞれの細胞には、それぞれ、全く同一の
DNAのセットがひとそろいそろっています。つまり目の細胞も、皮膚の細胞も、髪の毛の細胞もみんな同じ
DNAを持っているのです。
◇DNAは設計図のようなものということですが何を設計するものですか?
生命に不可欠なタンパク質を合成するための設計図です。その設計図は静的なものでなく、生物が生きて行く上で、非常にたくさんの種類のタンパク質の合成に役立たされ、そのタンパク質はそれぞれが違った目的と働きのため合成されます。ヒト細胞では数万種類のタンパク質が合成されるといわれています。そういう意味でDNAは生物の生命のある限り一分一秒の休みも無く働き続けている存在です。
◇同じタンパク質なのに、なぜ目は目で皮膚は皮膚で、髪の毛は髪の毛となるのでしょうか?
この問題は、現在、分子生物学上の最先端の問題となっています。
どうやら、細胞のおかれた環境と、ひとつの受精卵が卵割していく時期が重要な鍵を握っているらしいのです。つまり、生物の形質は、DNA
の設計図を基本にしてつくられているのですが、その生物
(細胞)
のおかれている環境によって、働き手であるタンパク質の種類と発現量、さらに発現する時期が違ってくるので、形質
(その細胞の性格、形状)
が変わってきてその部分のタンパク質としての個性がでてくるのです。
◇DNAとタンパク質の関係は?
タンパク質はアミノ酸から構成されています。このアミノ酸配列を決めるためのDNAの塩基配列のことを遺伝暗号といいます。遺伝子の本体はDNAですが、実際に体の組織をつくったり、体内の化学反応を進めているのはほとんどタンパク質です。 DNAをからだの設計図とすれば、タンパク質が実働部隊であり、DNAの情報もタンパク質に変換されなければ全く意味をなしません。つまりDNAが持つ遺伝情報(遺伝暗号)とは、タンパク質をつくるための情報ということなのです。
◇結局DNAがタンパク質をつくるのですか?
DNAはあくまでも設計図の役目に徹しています。実際にタンパク質を作り出すのは、DNAの情報をコピーするRNAが担っています。
◇細胞をもう一度説明して下さい。
ほとんどの生物の体は、「細胞」と呼ばれる目に見えないほど小さな構成単位が集まってできていてます。
細胞は、閉じた袋状の膜(細胞膜)の中に液体(細胞内液)が満たされ、様々な物(細胞内小器官)や核が浮かんでできています。 ヒトの細胞は前述したとおり成人でおよそ60兆あるといわれていますが、だれも正確に数えた人はいません。
◇その60兆個の細胞にすべて同じ
遺伝子が含まれているなんてとても信じられませんが?
細胞は分裂の都度、複製されたDNAを次々に受け取っていきます。それゆえたった一個の受精卵からはじまって、細胞分裂を繰り返し、全身ほとんど全ての細胞は、同じ遺伝子の組合わせを核の中にもつことになるのです。
◇乾癬の遺伝子があるといわれる第
6染色体を説明して下さい。第6染色体には遺伝子数として現在500個程度確認されています。
今回、ベーチェット病や尋常性乾癬に関連する遺伝子をそれぞれ突き止めたということですが、すでに、家族性パーキンソン病遺伝子や、組織適応抗原HLA白血球遺伝子群はこの第6染色体に存在することが確認されています。
◇ヒトゲノムの解析や乾癬遺伝子の発見は将来乾癬の遺伝子治療や完治治療につながりますか?
ゲノム解析が進めば、多くの場合乾癬の遺伝的側面や他の遺伝病の原因を突き止めることができると考えられていますが、最後に将来の見通しを皮膚科医の立場から東山先生からお聞きしました。
編集委員(森)
◇◇ 終章 ◇◇
乾癬は遺伝するのですか?
日生病院皮膚科 東山真里(文責)
朝日新聞(二〇〇一年二月十四号)の一面記事(カラー)で二重らせんの図とともに大きな見出しで「人体の設計図見えた。発病の仕組み、解明へ」の文字。
6番染色体の図の中に「乾せん」の文字を発見し、釘づけになった会員の方も少なからずおられると思います。あらたに関連遺伝子が見つかった病気としてリュウマチやベーチェット病と共に「乾せん」の名前が書かれていました。尋常性乾癬では多因子遺伝が推定されています。欧米では種々の遺伝解析技術を駆使して全染色体を対象にした尋常性乾癬の遺伝子の検索がすすめられてきました。これまでに尋常性乾癬の遺伝子あるいはその発症にかんする遺伝子の存在が第6染色体以外にも第1、2、4、6、8、17、20染色体などで報告されています。国内の乾癬患者については数年前より第6染色体のHLA抗原遺伝子領域の検索が、東海大学の猪子英俊教授らのグループにより進められ、今回の記事はその成果を示したものです。
HLA・C抗原遺伝子領域には膨大な数の遺伝子が存在しますが、猪子教授らはその中から4種の新しい尋常性乾癬に関与している可能性のある遺伝子を発見しました。これらのうち1種を除いて、他臓器にはなく皮膚にのみ特異的に発現していることがわかりました。このことは、これらの遺伝子が皮膚の独自の構造、機能に関与している可能性を示しています。乾癬患者の皮疹部と正常人の皮膚でこれらの遺伝子の動態がより明らかになると思います。このように尋常性乾癬と関連の深い遺伝子候補が発見されたことにより
€ どうして乾癬になるのか?
どの患者さんにどの治療が効果があるのか?
¡ 遺伝子の異常から生じている皮膚の細胞の変調を正常に戻すためにはどうしたらよいか
などの重要な問題解明へ強力な糸口になることが期待できます。しかし、遺伝子の異常・・・・・乾癬の独特の病態、すなわち表皮細胞の増殖亢進と免疫反応の異常の・・・・・の部分はブラックボックスです。候補遺伝子の発見はごく入り口で、乾癬の病態の解明や根治治療の開発までには、まだまだ膨大な研究過程が必要で道のりは長いと思います。
次に乾癬は遺伝するのかという点ですが、顔が親子で似ているのと同じように体質として子に伝わります。これは糖尿病、高血圧、喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患、と同じようになりやすい体質ととらえて頂ければよいかと思います。
体質があっても必ずしも発症するわけではありません。なりやすい体質に病気を悪くする環境因子が働いてはじめて病気になるのです。
家族にはだれも乾癬の人はいないのに自分だけが乾癬になったという人が殆どです。日本の統計では約5%の方に家族の誰かに乾癬が現れるといわれています。
親から子への遺伝ではこれよりも低いと考えられます。
乾癬の体質のある人が必ず乾癬になるわけではありません。種々の環境因子、悪化因子が重なり発症します。
遺伝子の解明が進歩することは歓迎すべきことですが、乾癬を悪化させたり、引き起こしたりしないよう日常生活の注意を守り、地道な治療を続けることが今のところ大切だと考えます。(東山)
**************************
◇遺伝子の解説なんて聞けば聞くほど、書けば書くほど疑問がわいてきて段々理解できるというよりもますますわからなくなるというのが実感ですね。不十分な解説のため「ますます」疑問が噴出してきた読者の皆さまのために、参考本を次に掲げます。
是非、一読して下さい。(編集員)
◎ヒトゲノムのしくみ
大石正道 著 日本実業出版社
◎ヒトゲノムのすべて
中原英臣 著 PHP研究所
◎DNA学のすすめ
柳田充弘 著 講談社
◎細胞のしくみ
長野 敬 著 日本実業出版社
◎遺伝子についての50の基礎知識
川上正也 著 講談社
◎生命の暗号
村上和雄 著 サンマーク出版
◎DNAとの対話
ロバート・ポラック著 早川書房
◎絵でわかる遺伝子とDNA
石浦章一 著 日本実業出版社
◎あなたのなかのDNA
中村桂子 著 早川書房
◎図解雑学DNAとRNA
岡村友之 著 ナツメ社
◎アミノ酸とタンパク質のはなし
軽部征夫 著 日本実業出版社
東海大学医学部分子生命科学
教授 猪子英俊
東海大学医学部分子生命科学 教授 猪子英俊
第6染色体HLA class1
領域に存在する HLA・C遺伝子座の対立遺伝子CW6が尋常性乾癬と相関することが知られてきたが、その相関は真の原因遺伝子が近傍に存在するため、強い連鎖不平衡により観察されている可能性がある。
近年遺伝子解析に頻用されるマイクロサテライトマーカーにより、詳細な遺伝子のマッピングが可能となった。われわれはHLA・C遺伝子座を含む1060kbについて、11個のマイクロサテライトマーカーを平均約100kbに1個の密度で設定し、日本人の尋常性乾癬患者と健常人から得た相関データを解析した。各マーカーの対立遺伝子頻度の相関解析ならびにハーデイー・ワインベルグ検定で絞り込んだ領域の祖先型ハブロタイプを推定し、その組換え体を調査した。
その結果、HLA・C遺伝子座からテロメア側、C1-2-6からC1-3-2のマーカー間54kbの塩基配列からコード領域を予測し、HCR、SPR1、STG、SEEK1の合計4個の新規遺伝子を固定した。
次に、RT・PCRにより各種臓器における発現を検索したところ、これらすべての新規遺伝子は皮膚組織において発現が確認された。さらに、HCR以外の新規遺伝子については皮膚組織特異的な発現を示した。
したがって、これらの新規遺伝子は尋常性乾癬感受性遺伝子の候補として考えられるものであった。現在は候補領域内のSNPs(single
nucleotide
polymorphisms)を検出し、さらに患者および健常人の皮膚を用いて新規遺伝子の発現を解析することにより、尋常性乾癬感受性遺伝子の固定を行なっている。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
第15回日本乾癬学会学術大会福島
シンポジウム「乾癬遺伝子プロジェクト現況と展望」より
飯塚万利子(伊勢原共同病院)
岩下賢一・梅澤慶紀・小澤明(東海大学医学部皮膚科)
猪子英俊・岡晃(東海大学医学部分子生命科学)
田上八朗 著 「皮膚の医学」より(中公新書)
◇昔から、皮膚を鍛えるといって、へちまやブラシでマッサージする人がいます。このような強い外力を与えつづけることは、角層を傷つけ、害になる物質の侵入を起こしやすくするだけでなく、表皮も傷つけますので、皮膚に炎症、つまり皮膚炎を起こします。
こういう皮膚炎は軽いため肉眼で見つけにくいのですが、炎症のあとにはメラニン色素が増えるため、皮膚の色がしだいに黒ずんできます。これを摩擦黒皮症とよびます。やせて鎖骨や肋骨のとびだした人では、そこに黒い沈着が起こり、骸骨を外からなぞったように見えます。
これはブラシによる摩擦で眼に見えない炎症が起きるほか、表皮の一部が壊れ、もっていたメラニン色素が真皮に落ちて、ちょうど自分自身の色で、入れ墨したようになるためです。もちろんこういう刺激をやめれば、日焼けの後と同じで、もとの皮膚にもどってきます。
ちなみに角層は、何もしないでも、一日に一層ずつ、表面から垢としてむけ落ちます。いくら気持ちがよいからといって、乾布摩擦や風呂で激しくこすりすぎないように。
どんなにこすっても、鉄のような皮膚に鍛え上げることはできません。
◇皮膚を掻くことや乾布摩擦は、角層や皮膚組織を傷つけ、むしろ皮膚炎を起こします。気持ちがよいからといって、風呂で激しくこすりすぎないように。こすっても皮膚は鍛えられず、傷つくだけです。
石鹸やシャンプーでよく洗うべき皮膚は、微生物の多い、頭、顔、首、手足、腋の下と股です。フケや脂漏性皮膚炎、また強い体臭を防ぎます。体臭も皮膚に棲んでいる微生物が原因です。
しかし、一日に何回も風呂に入り、上に述べた部位以外のところを石鹸でごしごし洗うことは、表面の角層の水分を保つ物質を洗い流してしまいます。その結果は水気のないかさかさした皮膚をつくることになります。春から夏は問題ありませんが、皮脂の分泌の少ない子供、女性、老人では冬は注意する必要があります。
そうでなくてもこういう人達は、寒くて乾燥した冬には皮膚が乾燥しやすいので、角層に適度な水分を保つべく、いわゆる保湿剤の入ったクリームを塗り、滑らかな皮膚にしておくことも余病を防ぐもとです。
田上八朗先生 医学博士
東北大学医学部皮膚科教授
大阪 みきタロウ
三重県の友人より3月4日(日)に榊原温泉にて三重県乾癬の会の学習会が行われるので一緒に参加しようとお誘いをうけました。
他県の患者会の催しに参加するのは少し気が引けましたが、思い切って行ってきました。
三重県乾癬の会では、夏は海水浴、冬は温泉湯治を主な年間行事とされており、今回はその冬の行事「温泉もみんなで入れば怖くない」というテーマの学習会でした。
場所は三重県中部に位置する久居市榊原温泉の国民宿舎「紫峰閣」で開催されました。近くには風光明媚な青山高原が広がっています。当日の参加は会員とその家族、合せて十七名の参加でした。学習会は午前十時から始まり、会長さんの開会挨拶に引き続き、元三重大学医学部教授、現市立四日市病院の谷口芳記先生の学習講演会がありました。講演会といっても和室の部屋に先生を囲んでの座談会形式で本当にアットホームな感じでお話をされました。先生のお話は乾癬の治療薬や副作用、悪化原因、治癒を目指すには・・・と多岐に渡り、最近話題のヒトゲノムにまで話が広がりました。お話の後、個々の疑問や質問に対して谷口先生が一人づつ丁寧に説明をして下さり、とてもなごやかな雰囲気の中で学習会が終わりました。楽しい昼食のあとは、待望の入浴タイムです。女性陣は五名が温泉に入りました。幸い他に入浴されている方が少なかったせいもありますが、「温泉もみんなで入れば怖くない」まさにこれを実感できた温泉湯治となりました。いつもは、脱衣所で服を脱ぐ時や体を洗う時、どうしてもまわりの目を気にしていましたが、この日は全くといっていいほど気になりませんでした。初めてお会いする方達ばかりでしたが、温泉につかりながら「どんな治療をしてるの?」とか「痒みはある?」などとおしゃべりに花が咲き、のぼせてしまいそうなくらいでした。温泉の泉質は、とてもぬるぬるしていて保温効果も優れているようで、入浴後も体がぽかぽかしてお肌がしっとりとしていました。入浴の後は、一息つきながらそれぞれに交流が始まりました。乾癬の情報交換をしたり、世間話をしたり、部屋から見える自然を眺めたり・・・。のんびり、ゆったりとした時間が過ぎていきました。いつの間にか午後3時。名残おしくもお別れの時間となり、皆さんと「何時の日にかまた会いましょう」などと声を掛け合い、数台の車に分乗して榊原温泉を後にしました。
「温泉もみんなで入れば怖くない」
これは私達にとってはとても心強い合言葉になるのでは?三重県乾癬の会の今回のテーマを強く心に残して近鉄電車で大阪に帰りました。車中では、座席シートに温泉のあたたかさと湯の香りを思い出しながら、心地よい疲れに眠気を誘われたようで、つい、うとうとと居眠りし始めたようです。
*************************
会報にレポートを掲載する旨快諾していただいた三重県乾癬の会の皆様に厚くお礼申し上げます。
みきタロウ
◇温泉紹介
清少納言ゆかりの名湯
清少納言の「枕草子」百十七段に「湯はななくりの湯、有馬の湯、玉造の湯」とうたわれています。このななくりの湯こそ榊原温泉なのです。ビロードのようにしっとりと肌になじみ、入浴後のお肌をつるつるにしてくれる温泉です。
◇泉質 アルカリ性単純泉
◇効能 慢性関節リウマチ、皮膚病、婦人病、糖尿病、神経痛、疲労回復、など。
注・榊原温泉の泉質は乾癬に効能があると推奨しているのではありませんので、宜しくご理解下さい。
(編集員)
第五回定例総会開催 平成十三年六月九日(土)
受付 正午より受付けています。
開会 午後一時より開会
一時〜一時三〇分まで 定例総会
一時三〇分〜二時まで講演会
講師 日生病院 名誉院長 山本昌弘先生
「漢方について」
二時〜二時三〇分まで
質疑応答
二時三〇分〜三時まで
会員による「乾癬体験談」
「死海での療養レポート」等
三時〜四時三〇分まで 懇親会
四時三〇分〜五時迄 自由懇談会
場所 日生病院 別館講堂(一階)
大阪市西区立売堀6丁目3の8
定例総会の内容
€ 事務局より事業報告
運営の現状と幹事の募集
懇親会
於:総会会場講堂にて
費用 三百円
交通アクセス
◎ 大阪市営地下鉄中央線
「阿波座駅」6番出口より徒歩3分
講師紹介 山本昌弘
◇略歴 大阪大学医学部卒・第9代日生病院院長・医学博士。日本内分泌学会・日本内科学会・和漢医薬学会で主要な役割を果たす。
日中医学協会員・ニューヨークアカデミー・オブ・サイエンス会員
◇業績
かねてから和漢薬の代謝作用と臨床応用に関する研究に取り組み、特に漢方生薬を代表する薬用人参・柴胡などについてはわが国を代表する評価を得ておられます。先生の「和漢薬の生化学的作用とその臨床応用に関する研究」は先駆的業績と認められ、平成7年度の和漢医薬学学会賞を受賞されました。乾癬の治療は最近、レチノイド、免疫抑制剤や新しい活性型ビタミンD3の開発などにより進歩を遂げています。しかし乾癬の患者さんの間では、より副作用の少ない穏やかな治療を望む声が強いのではないでしょうか?その中で漢方薬で治療したいと希望される方も多いと思います。しかし漢方の専門医が少なく、正しい漢方の知識、特に効果、副作用、内服方法などについて情報が充分とはいえません。東洋医学の基本概念なしには正しい漢方治療することは困難です。今回の学習会では長年漢方の分野での臨床研究されてきた山本昌弘先生に漢方の基本的な考え方について内科医の立場からお話しして頂きます。私自身(東山)は当院では乾癬の治療に漢方薬を用いた経験はありませんが、他施設での治療成績を少し紹介し、現時点での乾癬治療における漢方療法の位置付けについて皮膚科医の立場からお話ししたいと思います。(東山真里)
入会申込み先
大阪市西区立売堀6丁目3の8
日生病院 患者様サービス部
̃(06)6543・3581内線159
事務局 担当・小田救世代
郵便振替口座番号は
0920ー2ー155745
「大阪乾癬患者友の会」宛ですお近くの郵便局で申し込めば送ることができます。
年会費 3000円
会報をより充実させるため、皆さまのおたより(投稿)をお待ちしています。乾癬に関する医療相談、日常生活での疑問、民間療法の質問、疑問。詩や俳句、和歌など、取り上げて欲しい特集記事、各種ご要望など。投稿者は匿名やインターネット上のハンドル名などもお書きください。
●メールでの投稿あて先
e-mail:psonews
大阪乾癬患者友の会「会報編集部」宛
●郵便での投稿あて先
大阪市西区立売堀6丁目3の8
日生病院 患者様サービス部
大阪乾癬患者友の会編集部宛
匿名ご希望の方はその旨お書きください。ペンネームなども書き添えて頂ければ有難く存じます。投稿者の個人プライバシーを守るため、投稿記事掲載には充分配慮をいたします。お気軽にご投稿下さい。
|
大阪市 (田)
減反と米価に沈めど
季がくれば
我が家の田にも田植機はしる
静脈の浮きてしわしわ
手の甲よ
いまなお現役なかなかの迫力
|
- 創刊号 平成十一年五月発行
- ◇大阪に乾癬患者友の会誕生
- ◇友の会発足に寄せて
- 大阪大学医学部
- 教授 吉川邦彦
- ◇北海道「乾癬の会」相談役
- 北海道大学医学部
- 助教授 小林 仁
- ◇乾癬患者の手記 4編
- ◇友の会発足を祝います
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
- ◇北海道の友より熱きエール
- 「乾癬の会」会長 (梁)
-
- 第2号 平成十一年七月発行
- ◇第一回定例総会の報告です
- ◇講演「乾癬の症状と治療」
- 大阪大学医学部皮膚科
- 医師 佐野榮紀
- ◇コラム「死海」 小阪 博
- ◇第一回総会に参加して 手記3編
- ◇第一回総会参加感想文
- ◇「乾癬の会」で強くなった私
- 北海道「乾癬の会」事務局長 (岡)
- ◇乾癬に関するアンケート調査
- 中間報告
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
-
- 第3号 平成十一年十二月発行
- ◇三道府県による患者会PR活動
- ◇乾癬学習懇談会in京都
- ◇京都乾癬学習会感想文について
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
- ◇北海道より京の都へ旅日記
- 北海道「乾癬の会」(梁)
- ◇コラム「日光浴」 小阪 博
- ◇豊富温泉に行くには?
- 北海道「乾癬の会」
- 事務局長 (岡)
- ◇豊富温泉湯治を体験して
- 阪神虎夫
-
- 第4号 平成十二年三月発行
- ◇第二回定例総会のご報告
- ◇ご挨拶 友の会の皆さまへ
- ◇はじめての懇親会盛況でした
- ◇講演「ビタミンD3について」
- 大阪大学医学部皮膚科
- 医師 小林照明
- ◇第二回定例総会アンケート
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
- ◇しいたけはビタミンDが豊富?
- ◇乾癬関連のホームページ特集
- ◇キーワード「日光浴について」
-
- 第5号 平成十二年七月発行
- ◇第三回定例総会のご報告
- ◇講演「関節症性乾癬の臨床」
- 兵庫医科大学篠山病院
- 院長 立石博臣
- ◇乾癬に関するアンケート調査
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
- ◇ステロイド外用剤一覧表
- ◇角化症治療剤
- ◇ステロイド配合剤
- ◇ステロイド外用剤の薬効による
- 分類と血管収縮指数
- ◇関節炎闘病記 大分 るる
- ◇わたしの素顔 大阪 (田)
- ◇豊富温泉ツアーご案内
- ◇ドボネックス軟膏
- 新発売のお知らせ
-
- 第6号 平成十二年十月発行
- ◇全国患者会福島へ集う
- ◇乾癬学習懇談会in福島
- ◇講演「乾癬と日常生活」
- 社会保険福島二本松病院
- 皮膚科医長 佐藤守弘
- ◇コラム「エイコサペンタエン酸」
- ◇二十一世紀の乾癬治療
- 免疫、炎症の側面から
- 東北大学医学部教授 田上八朗
- ◇二十一世紀の乾癬治療
- 細胞の増殖、分化の側面から
- 大阪大学医学部教授 吉川邦彦
- ◇活性型ビタミンD3軟膏による
- combination およびsequential
- 治療の展望
- 自治医科大学皮膚科 中川秀巳
- ◇福島乾癬学会参加記 大阪 (岡)
- ◇ステロイドを考察する
- ◇豊富温泉湯治ツアーに参加して
- 大阪 (長)
- ◇わたしの素顔 大阪 (田)
- ◇第三回定例総会アンケート
- 大阪大学医学部付属病院
- 8階東病棟ナースチーム
-
- 第7号 平成十三年二月発行
- ◇第四回定例総会ご報告
- ◇2001年度世話役名簿
- ◇講演「乾癬治療の進歩について」
- 大阪大学医学部教授 吉川邦彦
- ◇インターネットオフ会顛末記
- みきタロウ
- ◇私の素顔 大阪 (田)
- ◇光線、紫外線療法
- 小林皮膚科クリニック 小林 仁
- ◇PUVA療法を受ける患者さんへ
- 小林皮膚科クリニック 小林 仁
- ◇闘病体験スピーチ(六名)
- ◇第四回定例総会アンケート報告
- ◇日常生活の工夫
- ◇平成十二年度収支決算報告書
- ◇平成十三年度運営予算書
◇今回の、遺伝子にまつわる特集は如何でしたか?
今後とも、遺伝子の問題は避けて通れない問題ですので、取り上げさせて頂きました。
「乾癬は遺伝するのか?」という絶えず沸き起こる皆さまの疑問に対して今回一応の決着をつけるため、基本的な遺伝子の情報を解説するとともに、東山先生から、皮膚科医の立場から「乾癬は遺伝するのか」について答えて頂きました。
受け止め方は個々によって違いがありましょうが、一応の答えを見出したのではないでしょうか?
乾癬があるために結婚など控えたりする若者があると聞きますが、残念な話しです。友の会の会合に参加して、多くの乾癬患者の既婚者が健康な子供を産み育てている事実をその目で確かめて下さい。
遺伝子情報については今後頻繁に新聞紙上を賑わすことと思います。
これをきっかけに遺伝子の知識を深めて頂いて、ガンや成人病などと遺伝子の関係など、乾癬以外の遺伝子情報に目をむけるきっかけになればと思います。
(編集員)
最終更新日
2001.7.24